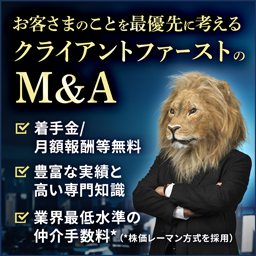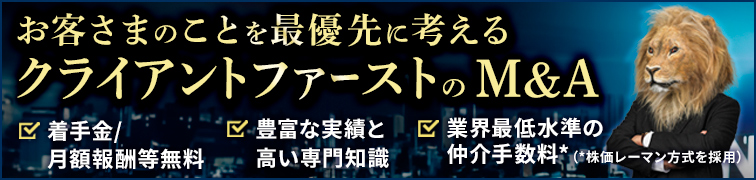更新日
事業承継の成功は企業に持続的な成長をもたらし、結果として社会全体にも貢献できます。その一方、後継者の不在や経済活動の鈍化といった、事業承継における問題が数多く浮上しているのが現状です。
本記事では、事業承継の重要性と問題点、リスクについて詳しく解説します。あわせて、事業承継を成功させるための具体的なポイントも紹介します。本記事を読むことで、事業承継のプロセスを理解し、自社の事業承継計画をより効果的に進めるための知識が得られるでしょう。
目次
1. 深刻化する事業承継問題とは
事業承継問題とは、事業の後継者不在により、会社が廃業せざるを得なくなるリスクです。特に、中小企業の経営者は高齢化が進んでおり、廃業した企業の約3割が「後継者難」を理由としています。
後継者がいなければ、経営状況や市場シェアが安定していても廃業するしかなくなり、従業員の雇用の場や、長年培ったスキルやノウハウを失うことにもつながります。

出典:事業承継を知る|中小企業庁
また、中小企業庁の調査によると、2021年6月時点での、日本国内企業における中小企業の占める割合は99.7%と高い数値です。そのため、後継者不在によって廃業する中小企業が増えれば増えるほど、日本経済を支える貴重な人材や技術が失われることとなり、国力の脆弱化にも影響が出ると考えられています。
事業承継問題は、日本経済全体にとっても深刻な問題です。この問題を理解し、適切な対策を講じることで、企業の持続的な成長と日本経済の安定に貢献できるでしょう。
2. 事業承継における問題点
事業承継には多くの問題点が存在します。特に重要なのが、後継者の不在と経済活動の鈍化です。
2-1. 後継者の不在
多いと思われる問題の一つに、後継者に適した人材がいないことが挙げられます。親族や知人・友人に候補者がいなければ、外部から経営人材を招聘(しょうへい)しなければなりません。その場合はゼロベースでの引継ぎとなり、時間も必要です。
また、自社に最適な後継者かどうかを判断するのも容易ではなく、見極める時間もかかります。仮に、親族や知人・友人、あるいは外部から経営人材を招聘できたとしても、経営者としての能力や素養がなければ、承継後の経営の不安定化につながります。
2-2. 経済活動の鈍化
もう一つの論点に「2025年問題」があります。事業承継における2025年問題とは、日本の経済成長を支えてきた団塊の世代が、75歳を超えることで発生する多くの問題です。
日本が超高齢化社会へ移行することにより、働き手の減少による社会保障負担の増加や、深刻な人材不足が進むでしょう。事業承継の観点からも、多くの企業経営者が75歳以上となることで、後継者不足に伴う廃業や倒産が増えてしまうと予測されます。廃業を選択する企業が増えれば、必然的に雇用は失われます。
これらの問題を解決するためには、事業承継の成功が不可欠です。
3. 事業承継で発生するリスク・問題点
事業承継ができなかった場合、あるいは実現できた場合でも、事業承継のあとに発生し得るリスクがあります。いずれのケースも多様な問題を含んでいますので、順番に把握していきましょう。
3-1. 事業承継ができなかった場合のリスク
事業承継がうまくいかないと、経営者や関係者に多大な負の影響が生じます。具体的なリスクは、以下のとおりです。
経営者に多額の廃業コストが生じる
事業承継が成就せず、経営者が廃業を選択した場合、さまざまなコスト負担が経営者に発生します。
資産の処分や退職金の支払いはもちろん、廃業時に負債があれば、処分した資産から賄う必要があります。それでも足りなければ、経営者が自身の財産から捻出し、さらに足りないとなると借入を起こしてまで工面する必要も生じる可能性があります。
また、従業員が廃業を機に失業するとなると、廃業前はもちろん、廃業した後にも経営者と従業員との間に軋轢やトラブルが生じる可能性もあります。経営者が廃業を選択した結果、従業員が雇用を失い、生活が圧迫されるためです。結果として、これらの問題は、経営者の引退後の生活に多大な影響を与える恐れがあります。
取引先に影響が及ぶ
廃業は自社のみならず、取引先にも大きな影響を及ぼします。例えば、廃業する会社が取引先企業の主要な取引相手である場合、取引先は売上の大部分を失うことになります。最悪の場合、経営難に陥り、取引先にも影響が及ぶという連鎖的な財務困難を引き起こす可能性もあるでしょう。
また、取引先にとって自社が主要な仕入先であった場合、取引先は経営のために必要な資源を確保できなくなり、新たな仕入先を探す手間が生じます。
3-2. 事業承継後に発生し得るリスク
事業承継が成功したあとも、新たなリスクが発生する可能性があります。具体的な内容は、以下のとおりです。
後継者と従業員が対立する可能性がある
承継後、後継者がこれまでの慣行を無視し、まったく新しい戦略や施策を行おうとすると、従業員の不満が生じる可能性があります。また、取引先からの反発を生むリスクも考えられるでしょう。
例えば、現経営者である50代の父親から、30代の息子に事業を引き継いだ場合、世代間による物事のとらえ方や考え方は大きく異なります。後継者が事業の立て直しやさらなる発展のため、従来とは異なる新たな戦略や施策を導入しようとしても、現経営者を長年支えてきた従業員には受け入れがたく、反感を買う恐れもあります。
経営に適した後継者が見つかっても、取引先や従業員の理解を得られなければ、事業承継を円滑に進めることはできません。
後継者以外から遺留分を主張される可能性がある
親族内承継では、遺言書などで後継者に会社の資産を相続する旨を定めることができます。しかし、複数の相続人がいる場合には、相続人に認められる最低限の権利である「遺留分」を請求されることがあります。
場合により、後継者以外の相続人から遺留分に相当する金銭などを要求され、後継者が承継した事業資産や株式を売却する必要が生じることもあるでしょう。こうしたケースは、経営を圧迫する要因となるかもしれません。
後継者の育成に時間がかかる
後継者の育成に時間を要することは、事業承継を阻む問題の一つです。引き継ぐ相手が決定すれば、事業や会社への理解を深めるための研修や、さまざまな知識やノウハウの伝達、社内外との関係構築などが求められます。スムーズな事業承継や、安定した事業運営のための育成には、多くの時間が必要です。
一般的に、後継者を決めてから事業承継が完了するまでの期間は「3年以上を要する」といわれています。経営者の高齢化が進むなかでは、後継者が決定しても、育成まで行うことができません。育成が不十分な状態で、事業を引き継がなければならない状況もあり、事業承継に踏み切れない理由となってしまいます。
3-3. その他、事業承継実施にあたって起こり得るリスク・問題点
事業承継の実施には、先行き不安で事業承継が進みにくい点や、手続きが複雑なうえに専門知識が求められるといった問題が挙げられます。
承継会社や事業の先行き不安で事業承継が進まない
承継会社や事業の経営状態に先行き不安がある場合、事業承継は進みにくくなります。現経営者が適任の後継者を見つけたとしても、後継者自身が事業承継を決断しなければ、先に進むことはできません。
承継会社の経営状況が芳しくない場合や、公的機関や地域とのトラブルを抱えている場合など、承継を拒絶される可能性もあります。
また、後継者は会社の資産と共に個人保証や負債も引き継ぐため、後継者にとってリスクが大きいと判断されれば、事業承継は進みづらくなるでしょう。
手続きが複雑で専門知識が必要
事業承継には複数のパターンがあり、親族内承継、親族外(社内)承継、M&A(第三者による承継)など、それぞれに適した書類の準備と手続きが必要です。
専門性が高く複雑であり、手続き面で相談できる相手がいないなどの理由で、事業承継をためらうオーナー経営者も多くいます。これらの問題を解決するためには、専門家の助けを借りることが有効です。
4. 問題点やリスクを踏まえて事業承継を成功させるには
事業承継を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
4-1. 早期に準備を行う
事業承継では、後継者の見極めから育成、取引先や従業員との関係性の構築、実務的な手続きなど非常に多くの時間と手間を要するため、数年単位で取り組むことが必要です。
まずは、事業承継の必要性を理解し、早期に準備を進めることが重要となります。健康上の問題が生じてから慌てて手続きを進めては、不十分な状態で後継者に引き継ぐことになってしまいます。ひいては、後継者探しが間に合わず、廃業となる可能性も否めません。
中小企業庁が発行している「事業承継ガイドライン」の第二章では、事業承継に向けた準備の進め方が紹介されています。このステップをもとに、早めの準備を行うことが、事業承継を成功させるための大きなポイントとなるでしょう。
4-2. 複数の手法を検討する
事業承継には、次のようなラインナップが存在します。
- 役員や従業員などに承継させる「親族外承継」
- 他の企業に売却する「M&A(株式譲渡など)」
- 上場して持ち株を売り出し、所有と経営の分離を図る「株式上場」
経営者としては、親族に承継させることを考えるケースが一般的です。しかし、上記のような他の選択肢の存在を知り、複数の手法を検討することで、より良い解決策にたどり着く可能性が高まります。
4-3. 国や自治体の制度を利用する
国や自治体では、事業承継のための優遇制度を設けています。下表の主な特徴を参考に、目的に応じて、自社に適した制度を活用しましょう。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| 事業承継・引継ぎ支援センター |
中小企業者からの相談対応やM&A候補案件の登録機関への橋渡し、登録機関で対応できない案件等の引き継ぎ支援を行う |
| 事業承継・引継ぎ補助金 |
事業承継を機に新しい取り組みなどを行う中小企業等および、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引き継ぎ支援を行う |
| 事業承継税制 |
円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度 |
4-4. 専門家のアドバイスのもとに進める
事業承継を成功させるためには、専門家のサポートを受けることが効果的です。事業承継では、法律や税金などに関する専門的な知識が求められます。
実際にどのような手続きが必要か、選択肢の優先順位は果たして適切なのか、などの見極めを経営者自身で行うことは困難です。足踏みをしている間に時間が経過し、結果的に承継が間に合わない事態にもつながります。
正確な手続きによる承継を行うためには、税理士や会計士、あるいは弁護士やM&A仲介会社などの専門家に相談し、アドバイスをもとに進めていきましょう。
5. まとめ
事業承継問題を引き起こす理由は多く、対応が遅れて廃業に追い込まれる経営者も少なくありません。廃業となれば経営者自身に多額のコストが生じるほか、従業員や取引先、さらには日本全体の国力低下にまで影響します。
適切な承継プロセスを経なければ、後継者と従業員の対立、相続人とのトラブルといったリスクや問題も生じます。事業承継を阻む障壁が多くあるため、スムーズかつリスクを回避して事業承継を行うには、専門家への相談がおすすめです。
事業承継に悩んでいる経営者様は、M&Aキャピタルパートナーズへぜひ一度ご相談ください。豊富な実績を持つアドバイザーが、手続きを円滑に進められるようサポートします。