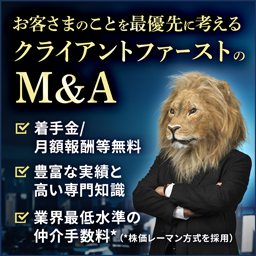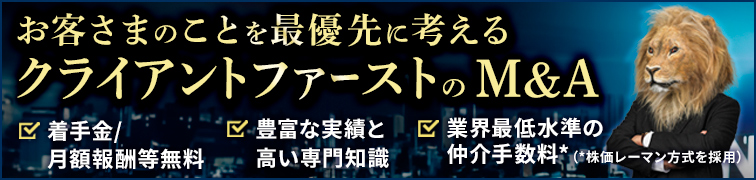更新日
一つの会社で複数の事業を行うのは、収益を安定化させるうえで必要なことですが、数が増えすぎてしまうとかえって経営効率が悪くなり、企業の発展を妨げてしまいます。そこで、組織再編に踏みきり、経営のスリム化を図る目的で行われるのが「会社分割」です。
会社分割には、新たに会社を設立して分割する「新設分割」と、切り離した部分を既存の会社に吸収させる「吸収分割」の2つがあります。本記事では、新設分割を行う際の手続きの流れや全体のスケジュール、注意点について解説します。
目次
1. 新設分割の種類
冒頭で述べたように、新設分割とは、既存の会社から切り離した事業を新設した会社に移転させる組織再編手法のことです。
新設分割は、1社から切り出す場合と、複数社から切り出す場合の2種類に分けられます。それぞれの手法について掘り下げて解説しますので、確認していきましょう。
1-1. 1社で行う場合
まず、1社から事業を切り離して新設分割を行う場合について説明します。
1社で新設分割を実施する際は、分割の対価を誰が受け取るかで、「分社型新設分割」と「分割型新設分割」の2種類に分けられます。
分社型新設分割

分社型新設分割とは、切り出した事業の対価を、分割元の会社が受け取る手法のことです。
会社分割の対価として、分割元の会社に対して承継会社の株式を交付するため、分割会社は親会社となり、承継会社は子会社となります。新設分割によって2つの会社が縦に配列されるため、「タテの会社分割」と呼ばれることもあります。
分社型新設分割は、複数ある事業の一つを独立させる場合などに用いられ、スピーディな意思決定を実現し、収益を明確にして責任の所在をわかりやすくすることが可能です。
なお、旧商法では分社型新設分割を「物的新設分割」と呼んでいたため、会社法が施行された現在でも、「物的新設分割」と称されることがあります。
分割型新設分割

分割型新設分割とは、切り出した事業の対価を、分割元の株主が受け取る手法のことです。
会社分割の対価として、分割元の会社の株主に対して承継会社の株式を交付するため、分割会社と承継会社は兄弟会社となります。新設分割によって2つの会社が横に並列されるため、「ヨコの会社分割」と呼ばれることもあります。
人的新設分割は、グループ会社内で兄弟会社を設立するときなどに用いられる手法です。
なお、旧商法では分割型新設分割を「人的新設分割」と呼んでいたため、会社法が施行された現在でも、「人的新設分割」と称されることがあります。
1-2. 2社以上で行う場合

次は、2社以上で新設分割を行う場合について解説します。複数の会社から事業部門を切り離し、新設した会社に対して事業を承継させる組織再編手法のことを「共同新設分割」といいます。
先ほどと同様に、その分類は2種類です。対価を得るのが分割会社である場合は「分社型共同新設分割」、分割元の会社の株主である場合は「分割型共同新設分割」といいます。
ただし、各会社(もしくは各株主)へ対価として支払われる承継会社の株式の分配比率は、承継される事業の価値をもとに算出されます。
2. 新設分割する際の手続きの流れ
続いて、新設分割を行う際の手続きの流れについて解説します。
手続きは「会社法」に関するものと「労働契約承継法」に関係するものとの2種類に分けられるため、それぞれについて順に紹介します。
2-1. 【会社法関係】新設分割の手続き

まず、会社法に関する新設分割の手続きから説明していきます。
分割計画書を作成する
会社が新設分割を行う場合、会社法では分割計画の作成が義務付けられています(会社法第七百六十二条・同法第七百六十三条)。したがって、新設分割を実施するために、まずは分割計画書を作成しなければなりません。
分割計画の作成により、分割会社から新設会社へ承継される権利義務の内容やその範囲等が特定されます。具体的には、以下の項目などを分割計画書に記載します。
- 新設会社の商号
- 所在地
- 事業目的
- 発行可能株式の総数
- 上記以外に定款に定める事項
- 役員の氏名(もしくは名称)
- 新設会社が承継する権利義務に関する事項
分割元の会社に事前開示書類を備え置く
分割会社では、事前開示書類を本店に一定期間、備え置かなければなりません(会社法第八百三条)。開示書類を備え置く期間は、以下のいずれかのうち、最も早い日から6ヶ月間と定められています。
- 新設分割の承認に関して開催される株主総会の2週間前の日
- 新設分割に反対する株主の株式買取請求に関する通知もしくは公告の、いずれか早い日
- 新株予約権買取請求に関する通知もしくは公告のいずれか早い日
- 債権者異議手続の公告もしくは催告のいずれか早い日
記載事項の具体例は、以下のとおりです。
- 新設分割計画の詳細な内容
- 当事会社の貸借対照表や損益計算書等に関する事項
- 分割会社と新設会社の債務履行の見込みに関する事項
- 分割対価の算定が妥当であることを証明する内容
株主総会の特別決議で承認を得る
分割会社と承継会社はどちらも、新設分割の効力が生じる日の前日までに、株主総会の特別決議で承認を得ることが義務付けられています(会社法第八百四条)。そのため、株主総会の招集通知を行うと共に、新設分割を実施する旨を株主に通知します。
なお、招集通知は、株主総会実施日の2週間前までに行うことが義務付けられているため(会社法第八百六条3)、郵送で通知する場合は、郵便物が到着するまでの時間なども考慮に入れておかなければなりません。
債権者保護手続き
次に、分割会社の債権者の利益を保護するため、債権者保護手続きを行います。新設分割を行うと、分割会社の資産だけでなく、債務も新たに設立される会社に承継されることになります。
債権者にとっては、資金力の弱い新設会社が新たな債務者となると、債務の履行に問題が生じる可能性があるため、債権者保護手続きが必要となるわけです。
分割元の会社は、債権者に対して「新設分割に異議のある場合は一定の期間内に申し出る」旨などを官報で公告します。官報に公告されてから最低1ヶ月間は、債権者からの異議申し立てを受け付ける期間を設けなければなりません。
また、知れたる債権者に対しては、官報による公告とは別に、郵送などによる個別催告が必要です。
株主・新株予約権保有者への公告・通知
新設分割は、会社に対して大きな影響を与える恐れがあるため、新設分割に反対する株主は、公正な価格での株式の買い取りを会社側に請求する「株式買取請求権」が認められています(会社法第八百六条)。
また、新株予約権の保有者は、分割会社の新株予約権の扱いが新設分割計画書と異なる場合、新株予約権の買い取り請求を行うことが認められています(会社法第八百八条)。
そのため、分割会社は株主や新株予約権の保有者に対して、新設分割の承認が成立してから2週間以内に、新設分割を実施する旨の公告と個別通知を行わなければなりません。
登記申請
ここまでの手続きが完了したら、分割会社と承継会社となる新設会社の双方で登記を行います。必要書類は、以下のとおりです。
| 新設会社 |
・新設分割計画書 |
|---|---|
| 分割会社 |
・代表取締役の印鑑登録証明書 |
分割会社と新設会社に事後開示書類を備え置く
分割会社については会社法第811条により、新設会社については会社法第815条により、新設分割に関する一定の情報の開示が義務付けられています。
これらの事後開示書類は、新設分割の効力発生日から6ヶ月間以上、書面もしくは電子データにて、会社の本店に備え置かなければなりません。
2-2. 【労働契約承継法関係】新設分割の手続き
ここからは、労働契約承継法に関する新設分割の手続きについて解説します。
労働代表者との協議
新設分割が行われる場合、分割会社の従業員のうち、切り出される事業部門に属していた従業員は新設会社へ転籍することになります。ただし、労働契約は新設会社と新たに結び直すのではなく、分割会社と交わしたものが承継されることが原則です。
従業員にとっては、労働環境や待遇などで変化が生じることとなるため、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」において、労働者との協議を行うことが定められています。
従業員との不要なトラブルを回避するためにも、時間をかけて、できるだけ丁寧な説明を心がけるのはもちろんのこと、合意を得た場合には書面で残しておくことなどが重要です。
労働者・労働組合へ通知する
分割の対象となる事業に従事している労働者や、新設会社に労働契約が引き継がれる予定の従業員に対しては、通知を行わなければなりません(労働契約承継法第六条)。
具体的な通知内容は主に、以下のとおりです。
- 当該労働者が分割事業に従事している旨
- 分割によって労働契約が新設会社に承継される旨
- 分割会社から新設会社に承継される事業の内容
- 効力発生日 など
これらの通知期限日は、株主総会の「2週間前の日の前日」までと定められています。また、株主総会を必要としない簡易新設分割の場合は、新設分割計画書が作成された日から起算して「2週間を経過する日」までに、通知を行わなければなりません。
なお、労働協約を結んでいる労働組合に対しては、以下の通知が必要です。
- 労働協約の承継の有無について
- 承継するにあたり、該当の労働協約の範囲について
- 承継する労働者の範囲について
異議申し出への対応
労働者には、承継される労働契約に対して「反対する権利」が認められています。
そのため、労働者への通知の翌日から会社が定める期日までの間に、異議の申し出があった場合は、新設分割の内容の見直しなどを行わなければなりません。
また、その期日に関しては、通知の日から最低でも13日間を空け、株主総会開催日よりも前に設定することが不可欠です。
3. 新設分割の手続きをするスケジュール例
次に、新設分割の手続きに関する日程の具体例を紹介します。
新設分割は、一般的に終了までに約2ヶ月の期間が必要です。したがって、例えば6月1日に手続きを開始した場合は、概ね以下のように進みます。
<スケジュール例>
| 手続きの内容 | 日付 |
|---|---|
|
分割計画書を作成する |
6/1〜 |
|
分割元の会社に事前開示書類を作成しておく |
6/1〜 |
|
労働者・労働組合へ通知する |
6/8〜 |
|
反対株主の株式買取請求通知を行う |
7/1〜 |
|
債権者保護手続きを実施する |
7/5〜 |
|
株主総会で承認を得る |
7/18〜 |
|
登記申請を行う |
7/25〜 |
|
新設分割の情報を開示する |
7/26〜 |
ただし、上記のスケジュールは大した問題も無く、関係者との調整がほとんど生じないようなケースのものです。実際に、このスケジュール通りに進むことは無いと考えておいたほうが良いでしょう。
なお、以下の条件を満たしている場合は、最短2週間で手続きを完了することも可能です。
- 新設分割の実施に関する株主全員の合意を既に得ており、すぐに決議を行える
- 新設会社へ承継する債務が無い
- 重畳的に分割会社も債務を引き受ける
4. 新設分割の手続きに関する注意点
最後に、新設分割の手続きにおける注意点について解説します。
4-1. 新設分割の効力発生日は登記申請日となる
新設分割の効力発生日は、新設会社の登記申請を行った日となります。しかし、法務局の営業日の関係上、土日祝日は「持参」「郵送」「オンライン申請」のいずれの申請方法でも、登記を行うことができません。
したがって、商業登記ができない休日は、効力発生日になりません。好きな日を選んで事業開始日としようとしても、新設分割の効力発生日に該当しない場合もあるため、こうした点には注意が必要です。
4-2. 公正取引委員会への届け出が必要な場合がある
共同新設分割を行うにあたり、事業の全部を分割する場合、分割の当事会社に国内売上高合計額が200億円超の会社と50億円超の会社がそれぞれ最低1社あるケースでは、公正取引委員会に届け出を行い、独占禁止法上の審査を受ける必要があります。
その場合、会社分割の届出日から30日を経過する日までは、会社分割ができません。ただし、公正取引委員会が認める場合には、30日間の会社分割の禁止期間を短縮することができます。
5. まとめ
新設分割を行う際は、手続きの内容や作成する書類などが、法律によって細かく規定されています。また、労働者や労働組合への対応も厳格に定められているため、いずれの手続きも適切かつ確実に進めていく必要があります。
こうした手続きや書類作成に不備があると、最悪の場合、会社分割そのものをやり直さなければならないため、手続きを行う際は専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
M&Aキャピタルパートナーズは、東証プライム上場のM&A仲介会社であり、弁護士や税理士なども多数在籍しています。新設分割の手続きに関して、疑問やお悩みのある方は、お気軽にお問い合わせください。